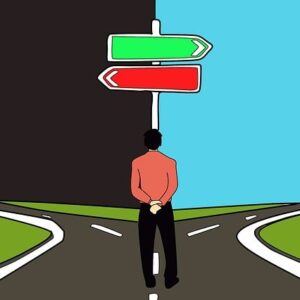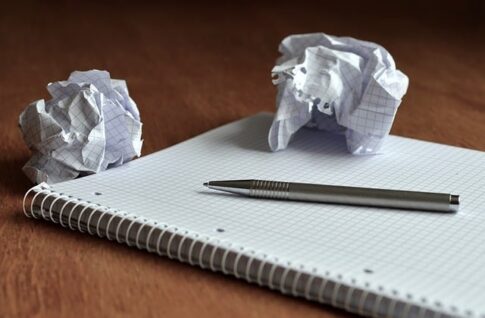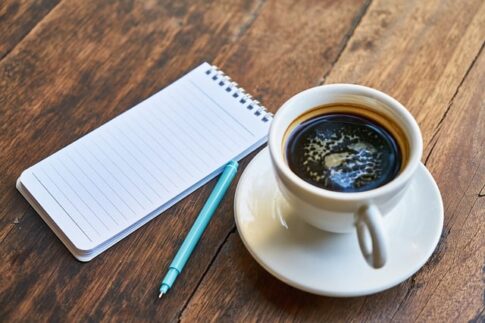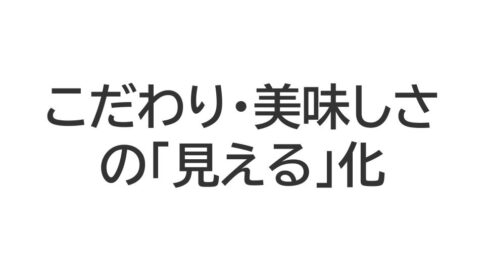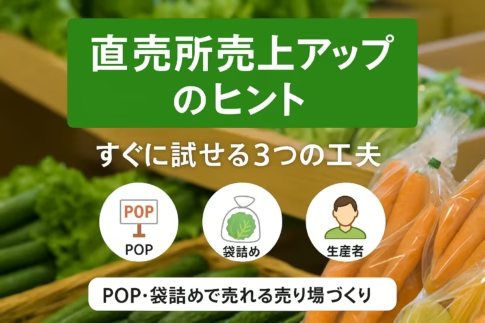道の駅や直売所を対象にしたセミナーの終了後、あるご相談をいただきました。
「道の駅内に産直コーナー(売り場)をつくりたいと考えています。どのような形で進めていけばいいでしょうか?」
ご相談くださったのは、セミナーに参加されていた道の駅の関係者さん。道の駅は、以前から運営されている。その施設内に、産直野菜を販売するコーナーを設けたい。ただ、計画をすすめていくにあたり、「商品(生産者さん)集め」に課題を抱えられていた。
実は、以前も道の駅内で、産直市場のコーナーを運営されていた。しかし、商品を出荷する生産者さんの減少から、産直コーナーの運営を休止。あらたに今回、リスタートする計画のなか、今回のご相談になったようです。
道の駅における、産直市の役割
道の駅によって、産直野菜を取り扱うお店とそうでないお店があると思います。私が前職、サラリーマン時代に働いていた会社が運営していた道の駅では、地元の生産者さんからあずかったお野菜を販売する産直コーナーがありました。
店頭に可動式のテーブルがあり、産直野菜を販売するコーナーがありました。しかし、例にもれずといいますか、野菜集めには苦労がありました。時季によって(特に冬場)、お野菜が集まりにくい。お店としては店頭という、一等地の売り場にありながら、商品が並んでいない。ボリューム感もなく、歯抜けになっていることも多かったです。
これでは、せっかくの産直コーナーも逆効果。本来であれば、お客さまを集める「集客装置」としての役割が大きい、産直野菜。道の駅として販売する、お土産商品に比べても利益率や単価の低い野菜を販売する目的。
ご想像のとおり、お客さまにお店へ足を向けていただくことです。たとえ単価が低くても、利益が薄くても、価格的に魅力を感じるお客さまの来店理由になる。品質管理などの手間がかかっても、それ以上のリターンを見込んで産直野菜を販売するわけです。
- 道の駅における産直市場(コーナー)の役割:集客、お客さまを集めること
直売所の課題と悩み
一方、産直野菜を販売する側(お店)にも悩みは尽きません。冒頭でセミナーに参加された道の駅のお話にもあるように、「生産者不足」は多くの道の駅や直売所など、産直野菜を販売するお店が抱える課題の一つではないでしょうか。
仕事柄、道の駅や直売所を運営される方々とご縁をいただく機会も多く、そのたび「生産者の高齢による、出荷者不足」のお話は耳にします。
実際、冒頭の道の駅さんも出荷者不足から、一旦、産直市場の売り場を閉鎖されていた。そして今回、あらためてリスタートしようと計画されているわけです。ただ、同じ地域でお店を構える以上、商品を出荷してくださる地元の生産者不足の問題は解消されていないはずです。
従来、道の駅や直売所では、地元の生産者さんから農産物を出荷してもらっています。そして、「●●の地域外の生産者からの商品は基本受け付けない」といった、商品の受け入れにあたって、ルールを設けられていると思います。それらのルールを改正しない限り、出荷者の対象は地元の生産者さん。
ですので、よほど新しい、若手の生産者さんを発掘してこない限り、特に地方では商品を出荷してくださる生産者不足の問題はついて回るのではないでしょうか(私が住む高知県も常にこの問題はつきまといます)。
道の駅「産直市場」設置にあたっての提案
冒頭でお話した、道の駅さんからのご相談。「いったん休止していた産直コーナーをあらためて、リスタートしたい」。そのお話をお聞きして、こういったご提案をいたしました。お話しした内容をざっと要約すると、下記のような内容です。
「産直販売を休止されていた理由はおそらく解消されていないはず。あらためてスタートするにしても、また出荷者不足から以前と同じような商品不足の問題が起きるのではないでしょうか。であれば、少しやり方をかえて、産直コーナーを設けられてはどうでしょうか。
通常の産直販売であれば、委託販売のかたちで生産者からお野菜を預かると思います。ただ今回は、すべて買い取りの契約で商品を仕入れて販売をする。さらに、ここがポイントになりますが、販売される商品は、野菜であれば、こだわり商品。さらには、単価の高い果物などに特化する。
もともと道の駅で産直市場を運営するのですから、来店されるお客さまには、お土産のニーズ(需要)がある。お土産として、野菜や果物をご購入いただく。お土産として購入したいと思える、お野菜や果物を販売されてはどうでしょうか?」
といった個人的な考えを共有いたしました。ではなぜ、このような意見を道の駅のかたにお伝えしたのか?
委託販売ではなく、野菜や果物を買取販売する理由
このブログでもよくお話ししていますように、30歳のころ、大阪の産直店で働いていました。そのお店で販売する農産物には、大きくわけて2つの種類がありました。
- 農協さんから送っていただく農産物
- お店が生産者から直で仕入れる農産物
前者、農協さんが送ってくださる農産物は、いわゆる直売所や道の駅で販売されているようなイメージです。ひとことで言うと、「生産者が値付け」をして、お客さまにご購入いただけると、お店に「販売手数料がはいる」委託販売の商品です。
一方、後者の「生産者から直に仕入れる」農産物とは、かんたんにいえば、仕入れ商品です。小売店が商品を仕入れるように、産直店であった私たちのお店も、生産者から商品を仕入れる。前者との違いは、「買取」仕入れであったこと。
従来の!?お店では、至極当たり前の話なのですが…、道の駅や直売所では、買取ではなく「委託販売」が主流(前職で道の駅のシステムを知ったとき、かなり驚きでした)。その委託契約ではなく、30歳の頃に勤めいていた産直店では、生産者さんから買取でお野菜や果物を仕入れていました。
ただ、買い取って仕入れる商品には、いくつかの条件がありました。
- こだわって作れられたお野菜や果物
- 農協さんが出荷してくださる商品では仕入れられないもの…など
たとえば、フルーツトマトであったり、こだわって栽培されたイチゴや柑橘類。農薬をつかわず、有機・自然栽培されたお野菜など。いってみれば、「生産者の顔が見える」商品として販売させてもらっていました。
道の駅の産直市場で「お土産ニーズ」を狙う
前述の通り、道の駅に来店されるお客さまには、お土産のニーズがある。お土産と言えば、500円、1,000円、1200円、、と価格帯が上がります。語弊のある言い方ですが、産直店にお野菜を買いに来られる感覚とは、かなり違います。
- 直売所:100円~250円くらいの価格帯
- 道の駅:500円~1200、1300円の価格帯
直売所でお野菜を買いに来られるお客さまは、「安くて、量の多いモノを」。この感覚でお買い物をされる方は多いのではないでしょうか。そのようなお客さまを対象にして、産直野菜を販売するのもひとつ。
一方、今回の道の駅さんに提案したのは、「お土産ニーズ」を狙っていくこと。そして、それに見合った商品(お野菜や果物)を仕入れること。
道の駅が立地する地域によって販売商品は違ってきますが、たとえば、高知県であれば、フルーツトマト・柑橘類のフルーツの栽培が盛んです。冬であれば、文旦(ぶんたん)といったグレープフルーツに似た柑橘があり、モノによりますが、10Kg箱で5千円前後で販売するケースが多いです。
10Kgが多いのであれば、5kg箱で販売してもいいでしょう。味見用の、小袋売りをしてもいいかもしれません。
いずれにしても見据えるのは、道の駅であれば、「お土産ニーズ」。お土産として、農産物をご購入いただく。それに合わせた、仕入れ。品揃えをおこなう。必然的に単価も上がり、販売の仕組みがうまくまわれば、経営的にも効率がよくなるのでしょうか。
まとめ
話が止まらず、どんどん脱線するので、まとめます。
セミナー参加いただいた、道の駅関係者さんから受けたご相談。
「道の駅で、産直市場(コーナー)を設けたい。どのように進めていけばいいか?」
こちらからご提案した内容。
「以前、出荷者不足で産直コーナーを休止されていた事情もあり、リスタートしても同じ状況を招く懸念がある。であれば、道の駅という強みを活かし、”お土産ニーズ”を狙う。産直野菜や果物をお土産としてご購入いただく。そのための仕入れや商品ラインアップを揃える。」
道の駅でお土産として、産直野菜・果物を販売するメリット
「従来の直売所のように、価格重視の農産物ではなく、お土産として販売をする。いいものであれば、高単価であってもご購入いただける。なぜなら、お土産としてご購入いただくから。必然的に、単価や利益率も上がり、労力や売り場スペースに対する費用対効果も上がる」と考える。